機械とヒト
人工知能についての議論が活発になっています。
わたしは、1980-90年代、「認知革命」=第二次AIブームと言われた時期に、「認知人類学」という分野に興味を持ち、人類学におけるもっとも基盤となる専門分野にしました。
University at Buffaloの指導教員であるCharles Frake先生は、アメリカにおけるethnoscience(その後「認知人類学」へと発展する領域)第一人者の一人で、「認知意味論」で最も優れた研究者の一人であるLeonard Talmy先生(大著"Toward a Cognitive Semantics"の著者)が、Buffaloの言語学部にいらっしゃり、創設された「認知科学研究センター」のセンター長を務めていました。わたしは、そのセンターのRA(Research Assistant)もさせてもらい、Frake先生、Talmy先生には本当にお世話になりました。

認知科学に関心を持っている社会科学者の一人として、今回のAIブームをみると、深層学習による自律的概念形成力をAIが持つようになったことは、やはり、一つの大きなブレイクスルーだと思います。
他方、囲碁や将棋のAIをみると、改めて「機械とヒト」との関係について、ヒトは、自分たちと同じレベルに達するか達しないかまで機械が発展したときに、一番驚き、興奮するが、自分たちのレベルを越えてしまうと、興味を失うと感じています。
ウサイン・ボルトと自動車を比べてみましょう。いくら人類最速のボルトといえど、100メートル走で、スポーツ仕様軽自動車にすら容易に負けてしまいます。あるいは、北島康介と競艇用ボートを比べてみても同じことです。北島選手は200メートルを2分以上かけて泳ぎますが、競艇用ボートであれば10秒もかからない。ですが、私たちは、ボルト選手の走り、北島選手の泳ぎに感動し、大きな声援を送るのです。
囲碁、将棋も同じで、ちょうど、AIの能力がヒトに追いつき、追い越そうとしていたために、私たちは興奮したり、危機感を感じたりしましたが、ヒトがAIに太刀打ちできなくなって、AI同士勝手にやってくれ!という状況にまでなれば、私たちは、ヒト対AIに関心を失い、プロ棋士同士の闘い、羽生対藤井に熱くなるのだと思います。
知性というヒトのみが高度に発達させてきた能力が機械にとって代わられるという意識が、AI脅威論にはあると思いますが、すでに記憶、パタン認識、微細な知覚など、ヒトの知性をはるかに凌ぐ機械はいくらでもあります。すると、自らの判断、意思をAIが持つようになることが、次の危惧となるでしょう。この点が、今後の大きな課題だと思います。
上述のように、一方で、ヒトは、ヒトと非ヒトとを区別し、ヒトに大きな関心を持つよう進化していることは間違いありません(また、ヒトの中でも「ヒトデナシ」を識別しようとする能力も発達させてきていると思います)。「心の理論(他者の心を措定し、推論する能力)」「感情」「身体」などがヒトがヒトであるために重要であり、AIがこうした要素を獲得するには、まだまだ時間がかかる(あるいは、原理的に獲得しうるかについても議論の余地がある)でしょう。
他方、ヒトの中に、AIを用いて、他の人々を支配しようとする試みが現実的危惧となる可能性もあります。また、身体・感情を持ったヒトが、AIを自らに取り入れる(サイボーグ化、ハイブリッド化)ベクトルも現実化してきました。ヒト、ヒトの社会・歴史は地層体であり、古い地層もいまだに機能する一方、新たな地層が加わって、より複合的、多元的になっています。ポスト冷戦期、デジタル、ネットワーク、ロボティクスは新たな地層を次々と生み出し、その目まぐるしい変化に、私たちは積極的に適応していく必要があると強く感じています。それが、社会情報学やデジタル社会学・人類学、科学技術社会論の新たな地平を構成していると思います。
最後まで目を通してくださり、ありがとうございました。
アラブの春はソーシャルメディア革命だったのか
小職は、拙著(木村忠正(2012)『デジタルネイティブの時代』平凡社新書)序章で、「アラブの春はソーシャルメディア革命だったのか」を論じました。「アラブの春」は、ソーシャルメディアと民主主義との関係について、多様な議論を引き起こしてきています。2010年代後半、民主主義の脆弱化、権威主義の拡張、ソーシャルメディアによる世論操作などがグローバルな課題となるなかで、「アラブの春」をどのように解釈するか、そこから何を読み取るかは、いまだに大きな意味を持ちます。
拙著は「デジタルネイティブ」に関する書物ですが、序章では、「アラブの春」について、多角的、複合的な分析を展開しており、それは、現在拡大している民主主義、権威主義、ソーシャルメディア、世論操作といった議論に資するものが依然としてあると考えております。ただ、書籍全体の主題が「デジタルネイティブ」であるため、「アラブの春」に関する議論は、関心を持ちうる方々への接点が乏しいかと存じます。また、小職の現在取り組んでいる「ネット世論」研究の基盤としても重要であり、序章の第一次草稿版をAcademia.eduにアップロードしました。以下のリンクは、英語表記になっていますが、PDFファイルの中身は日本語です。
拙著では紙幅の関係から省かざるを得なかった部分や異なる部分も少なからずあります。本稿を読み、関心をもたれた方は、拙著も読んでいただけるとありがたいです。学術論文等で言及される場合には、やはり、拙著を参照いただくようお願いいたします。
グローバル化の進展と文系大学院教育
この拙文も、立教大学社会学部、大学院社会学研究科に関心のある方、受験生、在学生、卒業生を念頭に書いています。この点、予め、ご承知おきください。
4年前に東大駒場から立教社会に移る際に考えたことを、改めて振り返り、前回の記事では、学部教育について、国立系大学が直面している課題を書きました。今回は、大学院教育・研究について、考えてきたことをまとめてみたいと思います。
図1は、2010年度の18歳人口を基点として、4年制大学入学者、4年度後(2014年度)の修士(博士前期)課程、専門職課程入学者、6年度後(2016年度)の博士後期課程入学者の概要をまとめたものです。

図1 2010年度18歳人口を元にした大学進学率・大学院進学率の模式化
中央教育審議会・大学分科会・大学院部会(2017年5月30日)「大学院の現状を示す基本的なデータ」スライド3
2010年度18歳人口122万の内、およそ半数の62万人が4年制大学に入学する計算です。この年齢集団で修士・専門職に入学するのが6.8万人(およそ18人に一人)、博士入学者が0.9万人(およそ130人に一人)。もっとも、社会人も加わっており、社会人院生数も含めれば、修士・専門職入学者は7.9万(およそ15人に一人)、博士入学者は1.5万(およそ80人に一人)です。今後も、社会に出てから大学院教育を受ける人たちが同様に出てくると考えれば、ある年齢集団が40歳、50歳になるまでには、社会人数を含められると判断し、これ以降、社会人を含めた数字で議論していきます。また、データは文系、理系両方を含みますが、拙稿の議論は、文系学術活動(+文系基盤の複合・学際系研究)を念頭においていることも予めご承知おきください。
表1は、これまでのデータをまとめ、2010年代と比較するために、1990年前後を併記したものです。1991年度から「大学院重点化」が実施されたため、1991年度修士(当時は専門職大学院は存在せず)となるよう、1987年度18歳人口を基点とし、大学・短大入学者、1993年度博士入学者数をまとめました。
表1 2010年度=18歳、1987年度=18歳を基点とした大学、短大、修士、博士入学者数推移(学校基本調査、人口統計)

今から30年ほど前(1987年度)、18歳人口はまだ拡大期にあり、4年制大学入学者率はいまだ4分の1、女性を中心に短大進学も相当多かったことが分かります。男女別に4年制大学入学者率を算出すると、男性35%に対して女性13%、女性の短大入学者率22%程度で、4年制大学・短大を合わせると、男女とも35%程度が進学している計算となります。高等教育の大衆化が進展してきていますが、修士入学者は3.5万、約190万人の集団に対して2%に満たず、博士となると1.1万、0.6%(170人に一人)に過ぎません。大学院教育がいまだ限られ、とくに文系では研究者養成を中心としていたことが伺えます。ちなみに私は、1987年度に修士入学、89年度博士進学で、大学院重点化直前の世代となります。
その後、18歳人口は、1992年におよそ205万人とピークを迎え、表1にあるように、20年近くたった2010年度には122万、2018年度118万とピークの6割程度になりますが、4年制大学進学率は上昇を緩やかに続けて、4年制大学入学者数は、2010年代60万人前後で一定しています。
さて、ここで問題です。東京大学大学院の修士・専門職入学者数、博士入学者数はそれぞれどのくらいでしょう?大学教員でも意外に知らない人が多いと思います。答えは、2016年度修士・専門職3202人、博士1238人です。学部の入学者が3176人ですから、修士・専門職は学部以上の「東大生」が入学していることになります。 つまり、学部は60万人の4年制大学入学者の内、約3千人(200人に一人)が東大生に対して、修士・専門職は7.9万人の内3千人(26人に一人)、博士後期は1.5万の内1200人(12人に一人)なのです
表2は、東京六大学と京大、阪大の8大学について、学部、修士・専門職、博士、それぞれの2017年度入学者数概数をまとめたものです。これら8大学は学部でも4万5千人、4年制大学入学者の7%を占めますが、修士・専門職になると2割、博士では4分の1近くになります。とくに、東大、京大、阪大の国立は、3大学院だけで、修士・専門職は10人に一人、博士は6人に一人にも入学者が達します。
表2 東京六大学+京大・阪大の学部・修士・博士入学者数概数(2017年度)
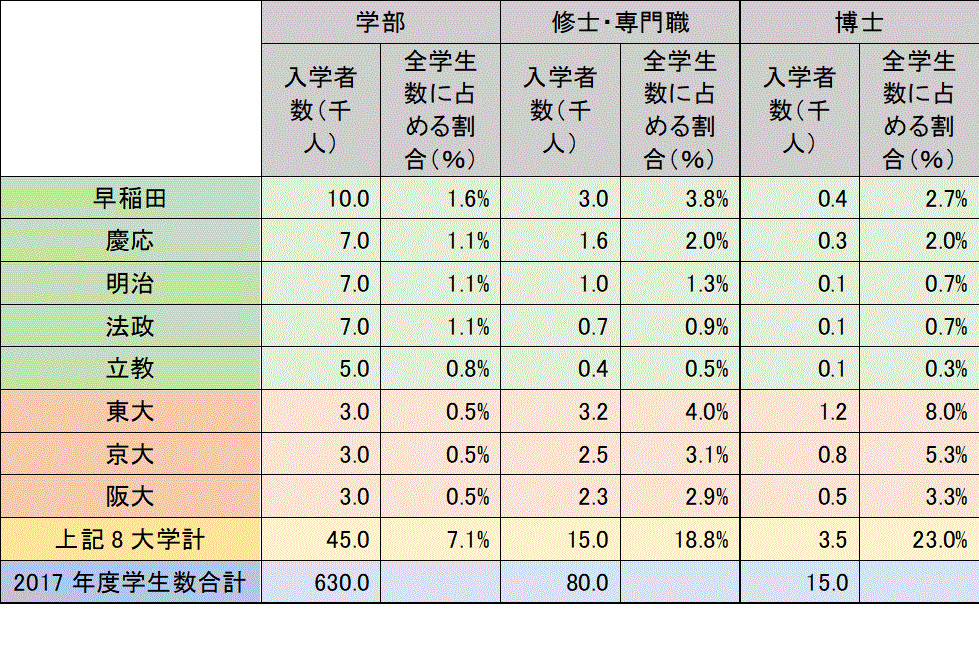
ところが、さらに驚くべきなのは、東京大学の博士入学定員は1697名で、志願者数1629名、入学者1190名だったということです。修士・専門職は入学定員3228名、志願者7141名、入学者3231名と学則定員を満たしていますが、博士課程は志願者数ですら定員に達しない状況です。もちろん、これは東大に限ったことではなく、東大ですらという表現がふさわしい。私学の雄で大学院も相対的に大規模な早稲田の場合でも、学則上は、修士・専門職入学定員3800人余り、博士定員は850人程度ありますが、表2で分かるように、そこまでは達しません。立教も、修士・専門職入学定員は550人を超えていますが、2017年度入学者は411人です。
日本の大学院教育、とくに博士に対する需要が、期待値(学則定員)よりも少ないことは間違いありません。図2は、文部科学省・中央教育審議会・大学分科会(第125回、2015年11月10日)配布資料の一部です。拙文をここまで読み進められた方々は、これに類した図をご覧になったことも多いのではないでしょうか。いずれのグラフも、日本で大学院修了者が少ないことを示しています。

図2 修士号・博士号取得者数の国際比較
出展:中央教育審議会・大学分科会(第125回、2015年11月10日)配布資料 資料3-3 「現在の高等教育改革の動向」関連資料と参考データ集(2/2) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2015/11/13/1364481_09.pdf
表1に示したように、1990年代に始まった大学院重点化にともない、日本の大学院教育も拡大してきました。しかし、ポスト冷戦期、グローバルな知識競争の拡大において、日本社会が後手に回っていることは否めません。表3は、1991年、2003年、2015年前後の時点における、亜欧米6か国の大学院学生数(フルタイム学生のみで、パートタイムは含まず)と人口をまとめたものです。
表3 亜欧米6か国の大学院学生数(1991年、2003年、2015年前後)(データ出展:文部科学省「諸外国の教育統計」、日本と中国の大学院における在学者数の推移(1990-2011年) | SciencePortal China)

冷戦が終結する1991年、西側世界が政治経済的にも、知識社会の面でも強い優位性を持っており、世界人口54億人の内、アメリカ2億5千万、西欧(英仏独伊蘭墺西葡ベルギー・スイス+北欧4か国)3億6千万、日本1億25百万が世界システムの中核(コア)を構成し、その中核7.35億人(世界の13%程度)の6分の1を日本が占めていたのです。大学院学生数でも、世界全体でまだ百数十万人に過ぎない中で、日本は10万人、実数で中国よりも多くの大学院生が研究に従事していたことになります。
その後、世界人口は64億(2003年)、74億(2015年)と拡大し、先進国と新興国中間層・富裕層を合わせて30億を優に超えるとも推計されています。それに伴い、大学院教育もまた拡大の一途です。他方、日本社会は人口も横ばいから減少期に入っており、大学院生数も20世紀には拡大しましたが、21世紀に入ってからは横ばい傾向にあります。研究者数全体についても同様です。図3は、文部科学省がとりまとめた主要国・地域における研究者数の推移です(文部科学省『科学技術要覧』平成29年版、46頁)。1990年代を見れば、日本は西側世界で、欧州、アメリカに伍して第三極の地位にあったと考えられます。

図3 世界各地域における研究者数の推移(文部科学省『科学技術要覧』平成29年版、46頁)
しかし、21世紀に入ると、日本の研究者数は80~85万人程度で頭打ちとなる一方、EU、アメリカ、中国が三極を構成している様子を見て取ることができます。 このように、冷戦終結期から2010年代までを振り返ると、冷戦終結まで、日本社会は冷戦構造で利益を享受していたのが、冷戦の枠組みが外れ、世界規模で優位性を巡るプレイヤーが増大していく中で、徐々に相対的地位が低下してきたと考えることができます。
先ほど、ポスト冷戦期、日本社会は、グローバルな知識競争の拡大において、「後手に回った」といいましたが、それは、日本社会全体が、先進国の中で先頭を切って、老成社会に突入しているという歴史的文脈に大きく規定されています。 ここで私が大きな問題と感じてきたのは、私自身も含め、日本の政策立案者、大学・研究機関で中堅以上の研究者たちは、どうしても、1970年代、1980年代の日本のプレゼンス高揚(東アジア研究のハーバード大教授Vogelが1979年 ”Japan as Number One: Lessons for America” を著した)、上述のような欧米日三極構造での日本の学術というイメージに支配されているのではないか、ということです。だから、世界大学ランキングに振り回される。しかも、この「ランキング」という概念は、ピラミッド型の階層性をどうしてもイメージしてしまう。
しかし、ここまで拡大したグローバル社会において、大学院レベルの大学院、研究機関もまた、「気球」のメタファーで考えるべきなのです。学部教育について議論した拙文で、日本の大学をピラミッド構造ではなく、気球構造でとらえる視点を提示しました。スペインの公的研究組織Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)による"Webometrics Ranking of World Universities"(http://www.webometrics.info/)のデータにもとづけば、2017年1月現在、世界全体での「大学」数は26,368にものぼります。CSISは独自の評価方法によるランキングを行っており、ここでは、トップ1000の国別ランキングで並べ替え、高等教育機関数が4000超で世界最大のインドまでを含んだデータを参考までに載せます(表4)。
表4 主要国における大学数とランキング上位大学数("Webometrics Ranking of World Universities" Countries arranged by Number of Universities in Top Ranks | Ranking Web of Universities にもとづき、筆者作成

これだけの高等教育機関が鎬を削っているわけで、グローバルにみれば、トップ1000でも上位4%にも満たないのです。もちろん、上位層と最上位層との間には厳然とした格差があると考えることもできます。ちょうど、アメリカ社会において、21世紀、上位1割の富裕層がアメリカの富の半分を占めるに至っているが、その富裕層1割の1%(全体の0.1%)こそが富の蓄積を加速させている実体である(Piketty『21世紀の資本論』)ように、上位1000分の1(上位20数機関)の高等教育機関は、巨大な財政力を誇ります。
表5は、米英のトップ10大学から7校(私が任意で選びました)と東大、NUSについて、学生数、年予算、基金をまとめたものです。 バークレーはカリフォルニア州立大という公立校であり、基金の規模は限られていますが、それでも2000億円程度の基金があり、年予算は東大の3倍を超えます。アメリカトップ私学は基金が1兆円を超え、年利1割程度で運用しているので、運用益だけで千億円単位となります。他方、東大は病院収入(470億円程度)を含んでおり、それを除くと2000億円強に過ぎません。もし、日本の政策立案者たちが、本当に、日本の国立大学をグローバル競争で1000分の1の勝者にしようとするのであれば、こうした財政力が必要であることを肝に銘じる必要があると思います。
表5 米英トップ10大学+東大・NUSの学生数、年予算、基金額
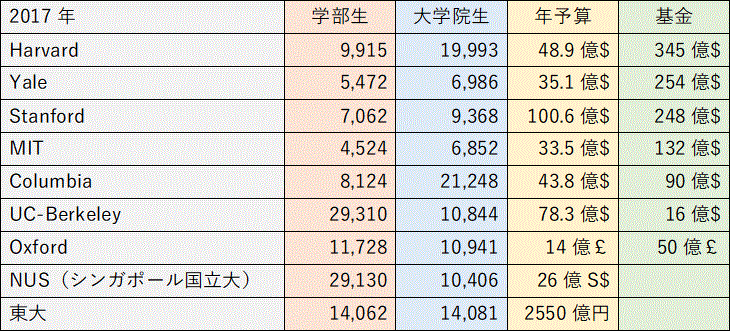
年予算、基金データは、各大学ホームページから筆者が整理。履修登録者数については、アメリカ各大学の多くは、https://www.collegetuitioncompare.com/による2017年秋時点でのもの。Oxford、スタンフォード、UC-Berkeley、NUS、東大は各大学HPから筆者が整理。2017年為替レート平均は、米ドル:1$=112円、シンガポールドル:S$=81円、英ポンド:1£=144円
他方、上位5%あるいは10%水準で競争するのであれば、日本の有力大学は、十分な資質を備えています。ここで、実際に、研究教育にたずさわる一教員の観点から、国立系を私学と比較すると、大学院教育において、次の2点が大きな課題だと感じていました。
- 学部教育と同様、設備、システムに対する投資が国立系は遅れがちである。
- 大学院重点化により、国立系は、大学院が所属先であり、大学院定員を満たす必要性が高いため、教員―学生比率において、大学院は国立系の方が私学よりも不利になる。
1)については、先の記事をご参照ください。 2)ですが、これは大学人以外の方にはわかりにくいかもしれません。ここでは、「社会学研究科」ということで、一橋大学院と立教大学院を比較してみたいと思います。
国立の場合、大学院重点化で、教員の所属は学部ではなく、大学院(研究科)となりました(近年は「学術院」という統合組織にしている場合もあると思います)。大学院が基盤ですから、学則定員数を埋めないと基盤が弱くなります。他方、私学の場合、もちろん、定員を満たすことができるに越したことはないですが、大学院は規模が小さく(教員の所属も基本的には学部です)、大学院教育は一対一のきめ細かい指導が学部以上に求められるため、定員を無理に満たそうとはしません。
表6は、一橋大学院・社会学研究科と立教大学院・社会学研究科の学生数を比較したものです(2017年度)。ここで質問です。それぞれの研究科専任教員数は何人だと思いますか?
表6 一橋・社会学研究科、立教・社会学研究科の学生数(2017年度現在、各大学HP資料から筆者作成)

この記事を書いている2018年5月現在、一橋63人(内特任5人)、立教30人です。一橋が多様な人材を擁していることはいうまでもありませんが、立教も専任教員30名というのは、社会学研究科としては国際的にみても大きな部類だと思います。ちなみに、社会学で最も著名な大学の一つであるシカゴ大学の社会学研究科専任教員は27名です(https://sociology.uchicago.edu/directories/full/sociology-faculty)。
こうして比較すると、教員数では立教は一橋の半分ですが、院生数は一割程度です。これは私学だからこそ、大学院教育では、学生にとって資源が潤沢であることを意味します。しかも、一橋院の志願者は2010年代200名台前半で推移し、実質倍率が2倍強であるのに対して、立教院は、志願者が2018年度入学者入試では延べ100名を越え(2017年9月、2018年2月の2回実施)、実際の入学者が16名なので、倍率は5倍以上になっています。立地や就学環境を考えると、立教の方に魅力を感じてもおかしくはない状況です。
実際、私の場合、立教に移り、大学院教育をより自分の専門に沿って、丁寧に行えるようになったと思います。もちろん、ここまでお話したことは、私個人の特殊な立場(文化人類学を出自として、インターネット研究に取り組み、ビッグデータにも積極的な研究者)による面も多いとは思いますが、日本の高等教育、大学院レベルの研究をグローバルに「気球」メタファーでとらえる視点や、国立、私立の対比など、目を通していただいた方に、少しでも参考になる部分があれば、幸いです。
また、大学院志望学生の皆さんに言いたいのは、大学院では、指導教員との関係が本当に大切だということです。これまで議論してきたように、日本において、大学院レベルでは、「ブランド」力は実質的な意味がなくなってきています。大学院レベルの研究では、指導教員の研究力・教育力、指導教員とうまくコミュニケーションできるか、円滑な関係を築けるかが決定的だと思います。自分のやりたいことと当該研究科教員とのマッチングを真剣に考えてほしいと思います。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
立教に移って4年度目~大学は気球・国立より優れた教育環境~
この拙文は、立教大学社会学部、大学院社会学研究科に関心のある方、受験生、在学生、卒業生を念頭に書いています。この点、予め、ご承知おきください。
私は2015年度に、東大駒場(総合文化研究科)から、立教社会に移りました。
前職は、私が日本で文化人類学を学んだ大学院であり古巣です。転職を決断する際には、日本の国立大学を取り巻く環境が大きく影響したことは間違いありません。国立大学が疲弊しつつあることについては、この拙文を読んでくださっている方であれば、周知のことかと思います。例えば、週刊東洋経済2018年2月10日号の特集、毎日新聞2018年4月からの特集が以下のリンクにあります。
研究劣化の真相 | 大学が壊れる | 週刊東洋経済プラス | 経済メディアのプラス価値
あるいは、「日本の研究力失速」について、鈴鹿医療科学大学学長・豊田先生のブログを読まれた方も多いかもしれません。
ここでは、これらの観点を踏まえながら、小職個人が何故、国立から私学に移ったのかをお話したいと思います。
大学教育は、学部教育と大学院教育があり、それぞれの側面で考えることがありました。まず、学部教育ですが、皆さん(とくに受験生や在学生)に知っておいてもらいたいのは、ここで私がイメージしている大学は、下の写真における気球のようなものだということです。
気球一つ一つが大学で、上下は、いわゆる受験力(受験で高得点をとる力)です。受験力は、個人の能力の一面に過ぎず、それぞれの人としての力は、まったく別であることはいうまでもありません。ここでは受験力だけで話をしますが、人間力や社会での活躍とは関係なく、独立したものであるのを前提としていますので、誤解ないようお願いします。
大規模な大学であれば、在学生たちの集団で、受験力は上下にかなりばらついています(気球は大きく、縦にも広がっているイメージ)。学部入学者数をみれば、早稲田1万、明治7千強、慶応・法政7千弱、中央6千、立教5千、阪大・東大・京大3千前後です。数千人もいれば、群を抜いて受験力の高い学生もいますし、いわゆる「偏差値」付近の学生、低い学生もいます。
入試というのは、ボーダーライン付近に多くの受験生がひしめき合っていて、合否判定は、コンマいくつの僅差です。コンマいくつということは、たまたま、どこかで一小問正解したか否かで、決定的な差になってしまうということです。結果は「合格」か「不合格」かの二択で、天国と地獄になってしまいますが、実際には、ある大学のトップ合格者たちとボーダー合格者たちとには、受験力で大きな差がある反面、ボーダー合格、不合格は「時の運」としかいえないものです。「偏差値」というのは、気球の重心であって、実際には、上述した私学であれば、かなりの学生たちの受験力は重なり合っていると考えた方が適切です。
ですから、とくにそれぞれの大学の受験生、在学生、卒業生に言いたいのは、入試は時の運が大きいのであって、自分の入学した(する)大学との縁は大切にして欲しいということです。気球の中でどう過ごし、気球自体をどう動かすかは、在学生、卒業生の活動如何だと思います。
さて、このように大学を気球に例えたとして、国立大学が直面している大きな課題の一つは、教育環境の整備だと思います。国立系は概して、施設・設備・システムについて、維持管理、修繕、更新、リノベーションの費用があまり考慮されません。そこで、新規に施設・設備・システムができたときはよいのですが、アップデートや修繕がままならず、新たに予算がつかないと徐々に時代遅れとなっていきます。
受験生は、是非、実際に大学に足を運んで、教室、図書館、各種施設を実際にみてください。おそらく、国立系は歴史を感じるでしょうが、老朽化したままという可能性もあることを認識しておいた方がいいと思います。さらに、21世紀の高等教育で最も重要なのは、情報ネットワーク環境です。私は2012年度にYale大学に客員研究員として滞在し、Harvard大学にも研究の一環で訪れましたが、その時点で、すでに両校では、キャンパス全域でWiFi接続が完備され、教室でもノートPC、タブレットを広げて授業を受ける形態が一般化していました。
現在は日本の国立系もだいぶ整備されてきていると思いますが、キャンパスが広い分、全域整備には時間がかかっています。その点、例えば、立教池袋キャンパスは、相対的に狭いことが幸いし、全域でWiFiネット接続が利用できます。さらに大切なのは、教学支援システムです。立教の場合、Google社のG Suiteを全面的に導入しており、メール、ドライブ、ドキュメント、カレンダー、フォームなどの機能が、すべて容量上限なく利用可能です。
立教での私の授業、演習はすべてペーパーレスです。ここでは演習を例にとります。演習で必要な文献、資料は、すべて、Google Driveでゼミ生たちと共有します。演習室には、貸出用PCが配備されているので、ゼミ生たちは、各自のPCを持参するか、演習室のPCを利用します。レジュメもDriveにあげてもらい、私のPCからプロジェクターに投影するとともに、各自のPCで閲覧してもらいながら、ディスカッションをします。社会調査アンケートを検討するときも、Google Formを利用し、各自ないしグループ毎にフォームを開き、共同編集をリアルタイムで遂行することができます。こうした演習形態は、私が実際展開したいと考えていたのですが、国立時代には実現できなかったものです。
講義系の場合には、Blackboardという授業支援システムを利用し、数百人規模の履修者でも、教材配布、小テスト、リアクションペーパーなどはBlackboardですべて行います。また、類似性判定機能があり、レポート類の不適切な引用等を容易にチェックすることが可能です。国立系の場合には、博士論文では類似性判定機能利用が必須ですが、それ以外は容易に利用できる環境にはないと思います。
ちなみに、2018年3月に公開された、私と同僚の井川教授との学部講義科目に関する対談が、立教大学教育開発・支援センターのニューズレター(MOVE)に掲載されています。よろしければ、ご高覧ください。
http://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/mknpps000000gu7p.pdf
さて、話を戻すと、このままでは、国立系は、学生、教員は一流でも、設備は二流ということになりかねない。私学はこうした点で、積極的に取り組んでいると感じます。昭和であれば、「ボロは着てても心は錦」でよかったかもしれません。しかし、すでに2020年代になろうとしている時期、国立がグローバルに戦うには、教育設備も先端的であるべきだという認識が醸成されることを私個人としては切望しています。
学部についてだけでだいぶ長くなってしまったので、大学院については、記事を改めて書きたいと思います。最後まで目を通してくださり、ありがとうございました。
